検索画面に戻る

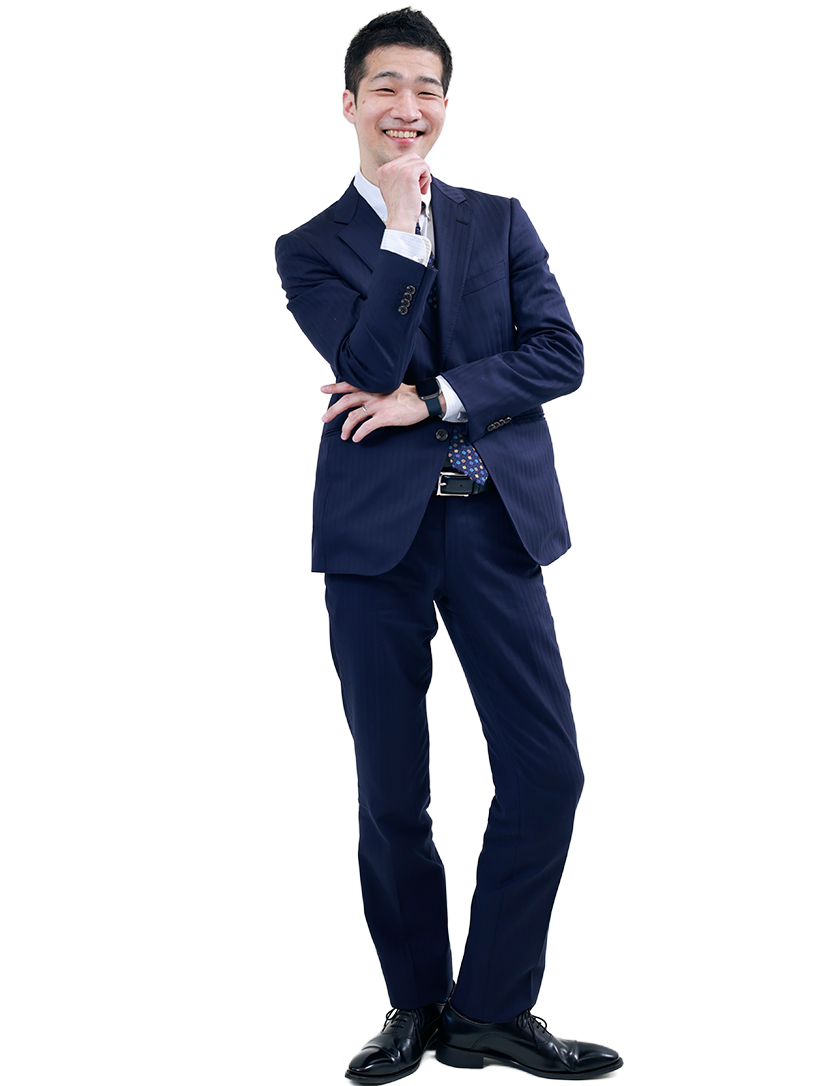


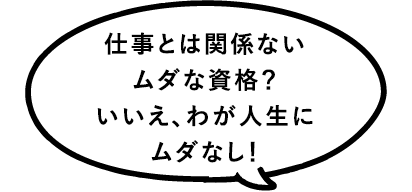

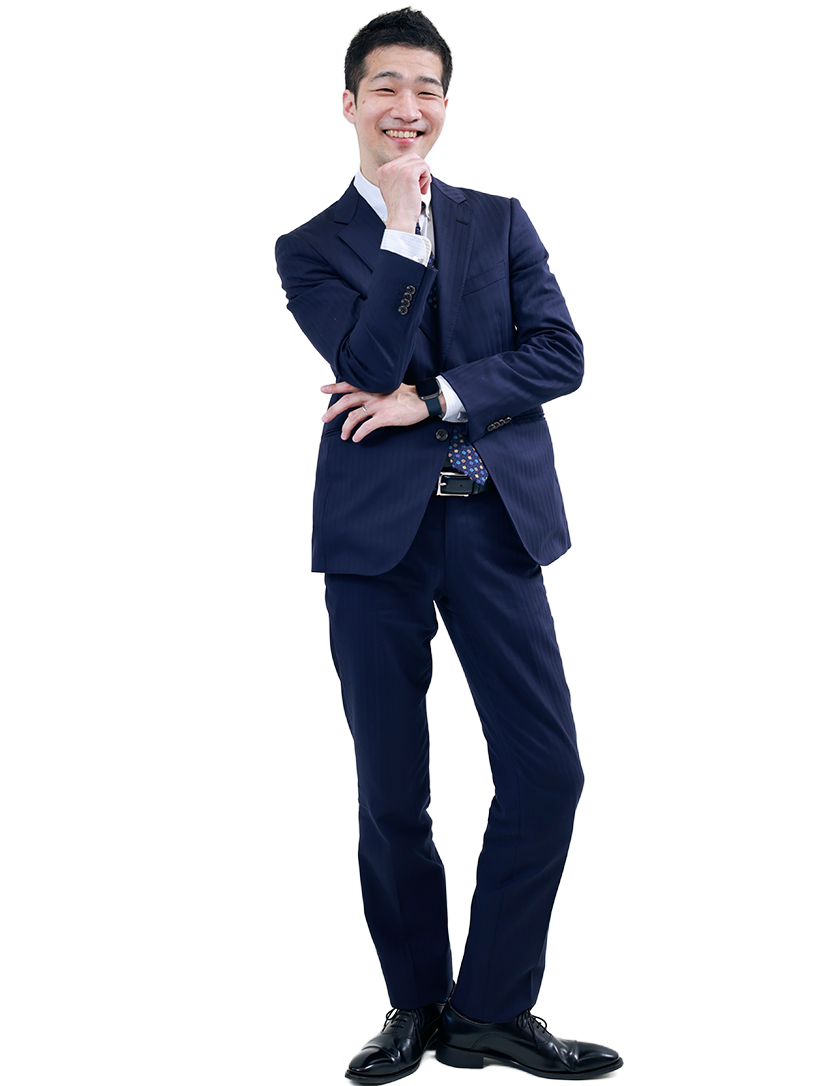


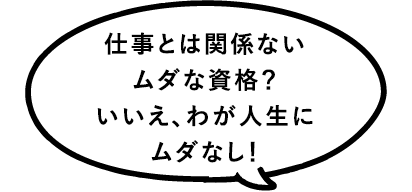
 この教員を見た方は
この教員を見た方は
こちらの教員も見ています
小川 真人准教授
Masato Ogawa
保健医療学部 リハビリテーション学科
理学療法学専攻
小川 真人准教授
Masato Ogawa
保健医療学部 リハビリテーション学科
理学療法学専攻
探求心が
服を着て歩いてる?!
疑問を燃料に難題に挑む
根っからの研究者
熱波師、FP、
コーヒーマイスターetc.
玄人はだしの多彩な顔を持つ
多面体星人

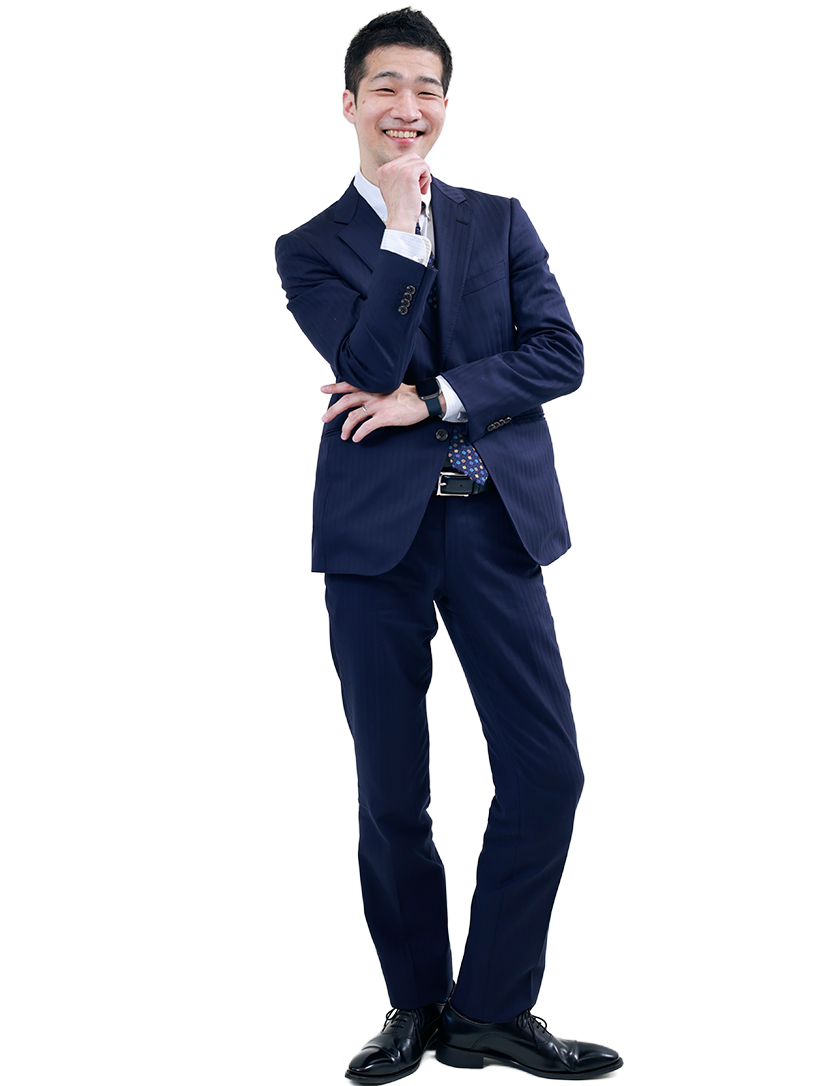


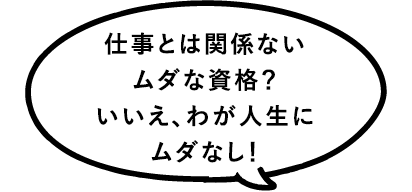
- 星人の特徴
-
- 分類
- 専門領域は内部障害理学療法、特に循環器領域、集中治療領域、栄養療法と理学療法。OHSU星では「循環器疾患患者に対するリハビリテーションの評価・介入に関する臨床研究」「急性期における栄養問題とリハビリテーション」を担当。
- 生態
- 信号の待ち時間がカウントダウンされるのがデフォルトの大阪生まれの大阪育ち。生粋の関西人らしく、横断歩道は先頭で待機・エレベーターでは行先階を押す前に閉めるボタンを押すのがマナーなど、マイルールを持っている。
- 弱点
- 効率化を考える合理主義者と言えば聞こえはいいが、実は単なる面倒くさがり(本人談)。ムダを嫌うあまり、せっかちになるのがウィークポイント。
- モットー
- 臨床での目線を大切に、患者さん一人ひとりから得られる情報を集積することで新たな問題解決へとつなげたい。目指すのは臨床の標準化!

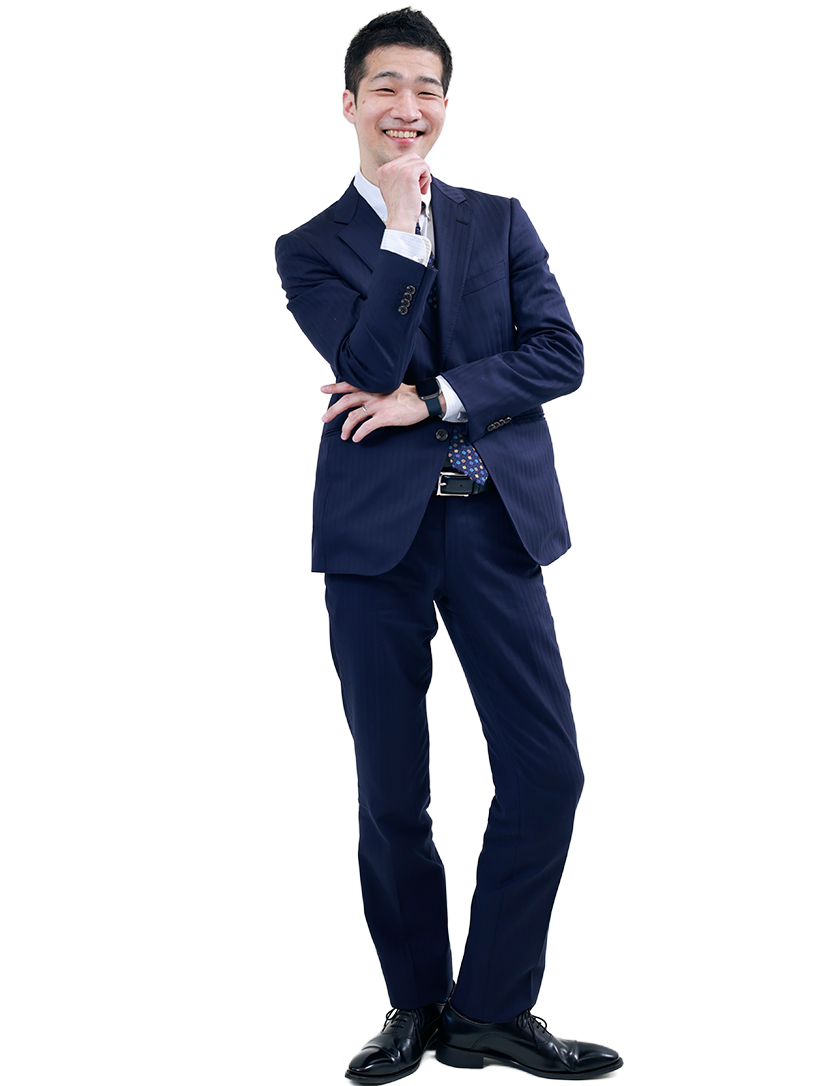


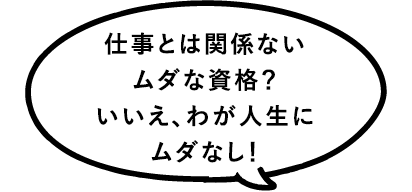
この先生に興味を持った方は
ぜひオープンキャンパスにご参加ください。
 この教員を見た方は
この教員を見た方はこちらの教員も見ています

- 関連リンク
- 理学療法専攻ページへ


















高齢社会で需要が高まる内部障害理学療法。
今から学び、専門性を高めませんか? 理学療法というと骨、関節、筋肉、神経など運動器のリハビリテーションを思い浮かべる方が多いと思います。しかし私が教えるのは、これらとは異なる内部障害のリハビリテーション。心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害など、体の内部に障害を抱える患者さんへのリハビリを専門としています。内部障害を持つ方は長期の安静を必要とすることが多く、運動を制限されることもしばしば。しかし、安静にしていると内部障害そのものや運動機能がさらに悪化するケースがあり、この悪循環を断ち切るために運動を行うことが重要になってきます。そんな時、安全を確保しながら適切な運動量を指導するのに役立つのが内部障害理学療法です。高齢化とともに内部障害を有する患者さんは年々増加しており、内部障害理学療法の重要性はますます高まっています。
また、内部障害理学療法は栄養療法とも密接に関わっており、栄養士と連携することが多いのもこの分野の特徴です。医師や看護師、薬剤師など多職種連携の要となることも多く、運動に伴う指導だけでなく、患者さんと接する時間が長いことから精神的な支えになる場面も多々あります。退院後にも相談を持ち掛けられたり、「こんなことができるようになった」と感謝されたり、私自身、臨床に携わっていた時は頼られる喜びを何度も味わいました。
とはいえ、内部障害理学療法はまだまだ認知度が低いのも事実。しかし認知度に反して重要度、需要は高く、この領域の知識があれば理学療法士としてひとり立ちした後も大いに役に立つはずです。クリニカルクエスチョン(臨床重要課題)をリサーチクエスチョン(研究課題)に落とし込み、答えを追求する。その成果は世界に向けて発信することが重要です。その中で、日本のみならず国際的な共同研究、教育活動へとつながっていきます。自分の抱いた疑問が新たな理学療法の確立につながるかもしれないというロマンを感じられるのは、未知の部分が多い内部障害理学療法だからこそ。ぜひ一緒にこの学問を究めましょう!